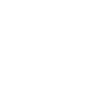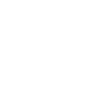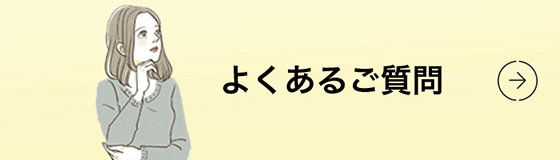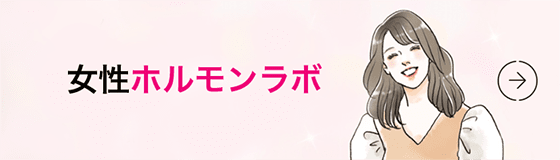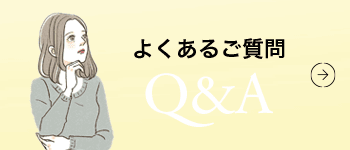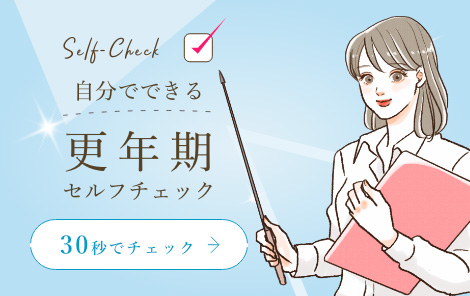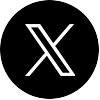PMS(月経前症候群)のはなし

PMS(月経前症候群)という言葉も最近ではよく聞かれるようになりましたね。
PMSとは、生理前の精神的・身体的な不調のことを指します。
まだまだ理解されにくい女性の生理前の症状や原因について詳しくご紹介します。
「もしかして、PMSかも?」と気になられいてる方には、簡単チェック方法などもご紹介していますので、参考にされてみてくださいね。

女性ホルモンバランスプランナー®の石井理夏(あやか)
PMS(月経前症候群)とは?
PMS(月経前症候群=生理前症候群)は、生理が始まる1週間くらい前からあらわれる精神的・身体的な不調のことで、英語のPremenstrual Syndromeの略称としてPMSと呼ばれています。
PMSの症状は、特に生理の2~3日前あたりから生理が始まるまでの期間に症状が強まることが多く、生理が始まると嘘のように症状があらわれなくなります。
(生理開始の2~3日後まで、症状が残る場合もあります。)
PMSは、排卵のある女性であれば誰にでも起こり得ます。
けれども、PMSの症状のあらわれ方には個人差が大きく、ほとんど気にならない人もいれば、日常生活に支障が出てしまうほど症状が重くなる人もいます。
補足:PMDDとは?
PMDD(月経前不快気分障害)は、生理前の症状のなかでもイライラ・気分の浮き沈みが激しい・不安といった精神的な不調が、日常生活に支障をきたすほど著しく重い場合に用いられます。
英語のPremenstrual Dysphoric Disorderの略称としてPMDDと呼ばれています。
PMS(月経前症候群)が起こる原因は?
PMS(月経前症候群)が起こる原因は、実はまだはっきりとは解明されておらず、医学的に明確な定義がありません。
明確な定義ができないのには、PMSの症状に個人差があることも大きいと考えられます。
というのも、分かっているだけでも約150種類にも及ぶPMSの症状が報告されており、原因究明が複雑なものになっています。
また、PMSの原因とされる説には10種類以上もの説があるといわれています。
この10種類以上ある原因説の中でも、PMSの症状の原因として最も有力視されているのが、2種類の女性ホルモン「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)の変化による影響です。
PMSが起こる時期と女性ホルモンの変化

PMS(月経前症候群)の症状には、排卵後のプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が深く関わっています。
排卵後、プロゲステロンの分泌量が増加して急激に減少するまでの時期を「黄体期」と呼び、この黄体期にPMSの症状があらわれます。
そして生理が始まり、プロゲステロンが必要とされない時期「卵胞期」になると、PMSの症状はあらわれなくなります。
PMSと2つの女性ホルモンの影響
生理前のプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量の変化は、水分代謝や脳内物質(GABA)に影響して、体調が不安定になるといわれています。
また、生理前はエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量が急激に減ることによって、セロトニンが低下し、ネガティブな気持ちを引き起こすといわれてます。
※脳内物質(GABA):不安を鎮めたり、睡眠を促進する効果がある脳内物質です。
※セロトニン:精神の安定や安心・平常心に働きかける脳内物質。別名「ハッピーホルモン」とも呼ばれています。
【あわせて読みたい】女性ホルモン基礎知識>>
【あわせて読みたい】エストロゲン・プロゲステロンの働き>>
心と体の「不機嫌」に寄り添うサプリメント
PMS(月経前症候群)の症状とは?
生理前にあらわれるPMS(月経前症候群)のさまざまな症状。
先述したように、個人差が大きく分かっているだけでも約150種類もの症状があるといわれており、その診断は難しいといわれています。
ここでは、数あるPMSの症状のうち、身体的な症状と精神的な症状の代表的なものをいくつかご紹介いたします。
PMSの身体的な症状
●頭痛・肩こり・腰痛
●関節痛・筋肉痛
●便秘・下痢
●吐き気・嘔吐
●むくみ
●お腹の張り
●乳房の張り
●だるさ・倦怠感・疲れ
●眠気・過眠・不眠
●肌荒れ・湿疹・吹き出物
●喉の痛みや違和感・扁桃腺の腫れ
●摂食異常(過食気味・拒食気味)
●体重増加
●めまい・立ちくらみ
●冷え性・寒気

【あわせて読みたい】PMSの症状の記事一覧>>
【あわせて読みたい】生理の基礎知識>>
PMSの精神的な症状
●イライラする・怒りっぽくなる
●気分が落ち込む
●情緒不安定になる・涙もろくなる
●不安・孤独を感じる
●憂うつになる
●無気力になる
●性欲が異常に増進・減退する
●集中力・判断力が低下する
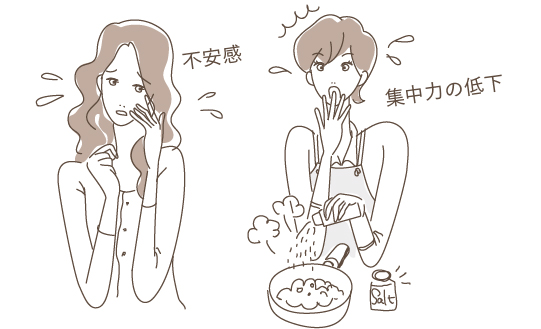
PMS(月経前症候群)の症状を強くしてしまう原因は?
| 食生活 | ビタミンやミネラル不足、お酒や甘いものの摂りすぎ、タバコなど |
| 体の冷え | 代謝が低く体が冷えている方 |
| 性格 | 几帳面、悩みやすい、細かい、つらくても我慢してしまう方 |
| 環境やストレス | 環境の変化が起きたときや、常に緊張している状態のとき |
PMS(月経前症候群)度をセルフチェックしてみましょう
「生理前の色んな症状に心当たりはあるけど…これってPMS(月経前症候群)なのかな?」
こんな疑問を感じていたら、あなたのPMS度をセルフチェックしてみませんか?
チェック項目の中から、あなたが生理前に感じている思い当たる項目にチェックを入れるだけ。
所要時間30秒ほどで、その場ですぐにPMS度のセルフチェック結果を確認することができますよ。
PMS度のセルフチェックをご希望の場合は、下記のバナーをクリックして、PMSセルフチェックにお進みくださいね。

PMS(月経前症候群)の治療法・PMSの症状を緩和するには?
PMS(月経前症候群)がつらいと感じている方は、婦人科で自分の症状を詳しく相談してみるとよいかもしれません。
PMSの治療として、病院で行われてる一般的な治療や自分でできるセルフケアをご紹介します。
| 低用量ピル | 避妊薬というイメージがありますが、月経痛、過多月経などのほかに、PMSの治療としても有効です。 低用量ピルは排卵をおさえるので、女性ホルモンの量が月経サイクルによって大きく変動しなくなり、PMSの症状を緩和させることができるといわれています。 |
| 漢方薬 | 悪いところを治すのではなく体全体を整える漢方薬は、不快な症状を改善するのに適しています。 「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」「加味逍遥散(かみしょうようさん)」「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」「抑肝散(よくかんさん)」などがPMSに有効とされますが、その人の体質によっても違ってくるので、漢方を取り扱っている病院や薬局で相談してください。 |
| サプリを飲む | PMSへの効果が期待できるといわれているチェストベリー。 チェストベリーは地中海沿岸や西アジアなどに自生するチェストツリーの果実で、ヨーロッパでは古くから婦人科系疾患の治療に用いられてきた西洋ハーブです。 |
生理前のつらい症状がPMS(月経前症候群)のせいだとわからず、悩む女性も少なくありません。
実は、私(石井)自身もそうでした。
ですが、生理周期を意識するなかで「イライラするのは自分のせいではなく、生理前だから」と思えると、気持ちが楽になりました。
PMSには個人差があります。そのため、ご自身の症状が理解されずに、悩みが一層深くなってしまうこともあるかと思います。
どうか一人で抱え込まずに誰かに話してみてください。
症状がひどい場合は、お医者さまに相談してみることもお勧めします。
そして、セルフケアでこころと体を休ませて、ご自身を大切にしてあげてくださいね。

参考文献
●PMS(月経前症候群)とうまくつきあう 著者/丸本百合子(百合レディスクリニック)
●生理前・生理中がラクになるPMS(月経前症候群)と女性のからだ 著者/池下育子